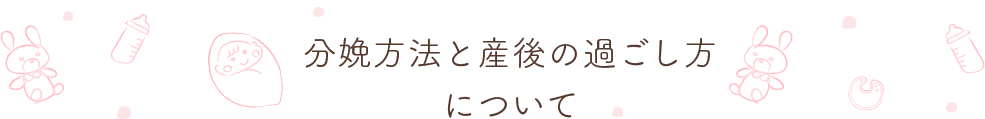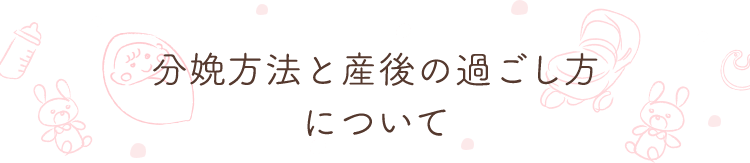分娩方法と産後の過ごし方
分娩方法と産後の過ごし方method & how to spend postpartum
-
経腟分娩の場合
お母さんについて 赤ちゃん・育児について 出産当日 出産後2時間は分娩室で過ごし、出血等の問題がなければ病室へ帰ります。 出産後のお母さん、赤ちゃんの状態をみて授乳を行います。希望された方には早期母子接触も行います。 産後1日目 外陰部を消毒し、問題なければシャワー浴が可能になります。 授乳室にて初回授乳を行います。母児同室が始まります。 産後2日目 退院までに新生児聴覚スクリーニング検査を行います。 産後3日目 採血検査・退院診察があります。 産後4日目 退院(午前中) 先天性代謝異常検査(採血)、退院診察があります。退院診察で問題なければ退院です。 ※詳しくは出産後にスケジュールをお渡しします。
-
計画分娩による
無痛分娩の場合お母さんについて 赤ちゃん・育児について 計画分娩前日 状況に応じて子宮口を広げる処置を行います。 計画分娩当日 診察後、分娩誘発を開始します。分娩進行状況に応じ麻酔を使用します。
出産後硬膜外カテーテルを抜去します。
出産後2時間は分娩室で過ごし、出血等の問題がなければ病室へ帰ります。授乳室にて初回授乳を行います。母児同室が始まります。
-
帝王切開の場合
(※緊急帝王切開の場合は手術前日・当日の予定が変わります)
お母さんについて 赤ちゃん・育児について 手術前日 入院後診察・除毛、麻酔科医から麻酔についての説明があります。
また、手術前後のスケジュールをお話します。手術当日 術前(前日からの場合もあります)より点滴をします。手術室でお小水の管を入れます。
手術中から間欠的空気圧迫法を行います。
術後6時間で水分摂取が可能になります。出生後すぐ手術台で面会ができます。その後病棟でご家族とご面会になります。
お母さんが病室へ戻ってきたらいつでもベッドサイドで面会ができます。
出産後のお母さん、赤ちゃんの状態をみて授乳も行うことができます。術後1日目 採血検査があります。初回歩行をします。その後お小水の管、点滴を抜きます。
十分に歩行できたら間欠的空気圧迫法は中止します。食事が始まります。低分子量ヘパリンの注射を行います。授乳室にて初回授乳を行います。母児同室が始まります。 術後2日目 術後1日目は清拭をさせていただきます。お傷が問題なければシャワー浴開始になります。 術後3日目 採血検査があります。 術後4日目 お傷のテープをはがします。退院診察で問題がなければ退院です(午前中) 退院までに新生児聴覚スクリーニング検査を行います。 術後5日目 採血検査があります。 先天性代謝異常検査(採血)があります。退院診察で問題なければ退院です。 ※当院では、予定(選択的)帝王切開で手術後の回復力強化プログラム(Enhansed Recovery After Surgery: ERAS)を取り入れています。 手術当日から飲水、歩行開始の場合もあります。
防災の取り組み
地震・火災などで避難が必要な際はお母さんにスリングで赤ちゃんを抱っこしてもらい、避難します。
スタッフは定期的に避難訓練を行い、緊急時に備えています。